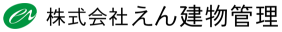建物に寄り添う
私たちは、マンションが大好きです。
時代の流れとともに人の暮らしが様々に変化するなか
入居者様が「安全」で「快適」に暮らせる
未来に残るマンション管理のお手伝いを続けてまいります。


アクセス
お問い合わせ
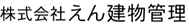
- 福岡市博多区住吉3丁目12番1号 えん博多ビル
-
 092-260-5350 電話をかける
092-260-5350 電話をかける
- 営業時間:平日 10:00~17:00
 メールでのお問い合わせはこちら
メールでのお問い合わせはこちら